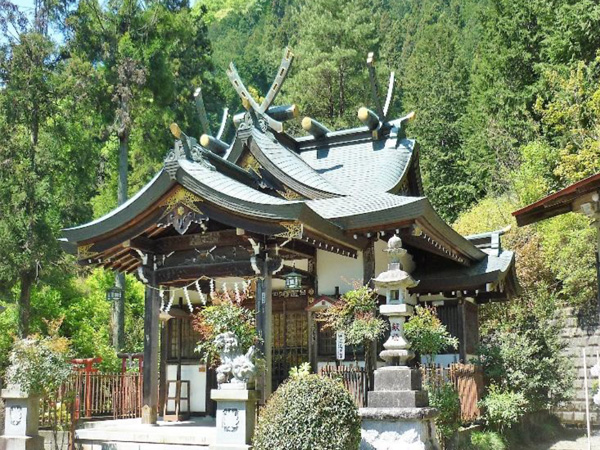八碁連だより380号(6月号)
囲碁雑感
恩方同好会会長 藤森 力
どこかの公園で桜が満開となり、花吹雪の中で、若者達の昔と変わらぬ宴会の様子を今朝のニュースが報じていた。
そこには戦争も、コロナも無い平穏な当たり前の日常があった。
恩方同好会も3月24日、総会を開催し、新年度より4年ぶりに通常活動に戻ることを確認した。
コロナ禍の3年間は、諸々の規制があり我々高齢者にとって辛い日々だった。
しかし、様々な工夫をした囲碁三昧の日々,それなりに充実した囲碁人生を謳歌したようにも思う。
最近感じるのは囲碁の奥深さである。昭和の初期呉清源と木谷實が、信州は地獄谷にこもり新布石を発表、囲碁界をアッと云わせた。
AIによる新布石はそれをはるかに上回る変化で、囲碁を考え出した先人達もさぞ驚いているであろう。
芝野虎丸さんや中村菫ちゃんの棋譜を見ているとAIの考えを随所に取り入れており、これからの囲碁は更に激しく進化するものと思われる。
そもそも、このように素晴らしい囲碁というゲームは、いつから始まったのかと調べて見ると、2千年前とも4千年前ともいわれている。
先人たちが紙も筆記用具もない時代にこのようなゲームを考え、楽しんでいたという事はにわかに信じがたい。
それを、4~2千年前に考え出したその頭脳には、ただ、ただ感服するばかりである。
同時に、いまだそれを熟しきれていない自分、勉強の余地は十分すぎるほどある。
囲碁はコウがあるから面白いと言われるが、上手と対局する時にコウを避けたい自分がいる。
また、目算が正確さにかける。勝ったと思っていた碁が、並べてみると2,3目足りないなんて事もしばしばある。これでは勝率も上がらない。
テレビの囲碁解説者は、まだ中盤なのに「白の半目勝ち」などと神業に近い目算をする。そこまで行かなくても、せめて寄せ前におおよその見当を付けたい。
AI布石もいいがその辺りを克服し、先ず従来の布石の意味をきちんと学ぶことが棋力向上に最も有効なことのように思われる。
まだまだ、老いてはいられない。